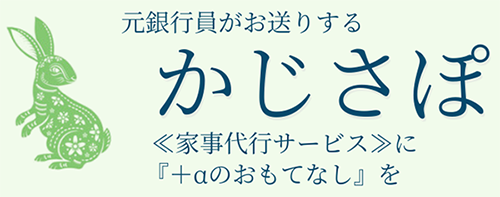おはようございます。とても寒い朝ですね。来週にかけて10年に1度の寒波が襲来するようです。皆様、体調には十分ご留意ください。
さて、ランセットという世界的に有名な医学書雑誌に認知症予防における重要な14項目が発表されました。世界中の認知症最新研究をまとめた報告書ならびに科学的根拠に基づいた14の認知症リスクが紹介されています。具体的には教育機会の不足・難聴・うつ病・頭部外傷・運動不足・喫煙・糖尿病・高血圧・肥満・過剰飲酒・社会的孤立・大気汚染。今回、LDLコレステロールが高い状態・視力障害も初めてリスクに加わりました。これらを個人が改善したり、社会で対策できれば、認知症を最大で45%予防したり、発症を遅らせることが可能だという画期的な記事です。
認知症を予防するには、ひとりひとりが正しい知識を持って、予防に取り組むことが重要です。科学的根拠に基づいた認知症のリスクと対策を参考にして、心当たりのある認知症リスクを改善し、認知症予防に生かしましょう。「かじさぽ」でも意識して認知症予防対策を講じていきます。
報告書では、私たちの生涯が、3つの時期、具体的には①18歳まで、②18―65歳まで、③65歳以降に分けられ、それぞれの時期に認知症につながる14のリスクがあることが示されています。そして、それぞれのリスクがどの程度なのかを示し、これらのリスクを改善・対策することで、認知症の発症を最大45%防いだり、遅らせたりできる可能性があるということです。
まず、18歳までの時期の認知症のリスクとしては、①教育機会の不足が挙げられています。教育機会の不足を解消することで、5%認知症を予防できるということです。脳は神経ネットワークのかたまりです。たくさんのことを学ぶことで神経ネットワークが強化されると、例えば脳の一部に支障が起きても別の部分が補うなど、認知予備能を高められ、認知症予防につながると考えられています。教育について何か特別なものが必要なのかというと、そうではなく、日本で受けられる学校教育で十分です。海外の研究では、文字の読み書きができないことが認知症のリスクにつながるとも言われています。また、若い時期も大事ですが、年をとってからも同様で、新しい知識などを学び続けることは認知症予防に大切です。
次に18歳から65歳までの時期に注意したい認知症のリスクです。この時期、まず大切なのが、②難聴、そして、③高LDLコレステロール、いわゆる悪玉コレステロールです。対策をとることで、それぞれ7%認知症を予防できます。また、④うつ病、⑤頭部外傷も認知症のリスクで、対策できれば、それぞれ3%予防できるといいます。実は、認知症のリスクについては、2020年にも報告書が出されていますが、その時は、高LDLコレステロールはまだ科学的根拠が不十分とされていましたが、今回、データが集まり、認知症のリスクの一つとなりました。LDLコレステロールの値が高いと、動脈硬化を起こし、脳の血流が低下し、血管や神経細胞のダメージにつながります。また、血管性認知症につながる脳卒中のリスクも高くなります。さらに、アルツハイマー病に関わるアミロイドβと呼ばれるたんぱく質が蓄積しやすくなるとの報告もあります。LDLコレステロールが高い人は食事・運動など生活習慣の改善とともに、必要に応じて治療薬であるスタチンなどを使い、適切な値に下げることが大切です。難聴も認知症のリスクです。耳が聞こえにくくなると、人とのコミュニケーションが不自由になります。会話・やりとりができなくなり、気分が落ち込んだり、ときに社会的な孤立につながったりします。また、耳からの刺激が少なくなり、脳の働きや認知予備能が低下します。難聴にならないためにも、例えば「ヘッドホン難聴」に注意しましょう。ヘッドホンやイヤホンなどで大きな音などを聞き続けていると、難聴につながることがあるのです。また、高齢になり、難聴になってしまっても、補聴器を使うことで認知症発症のリスクを下げることができます。例えば、12万人以上が参加した研究を分析したところ、補聴器を使用した難聴の人は、使用しない人と比べ、認知症のリスクが17%低かったことがわかりました。また、耳の病気、例えば、メニエール病・中耳炎などをきちんと治療することも難聴にならないために大切です。
5項目まで紹介しました。残りの項目は次回にお話しします。